
本名:三浦知壽子 洗礼名:マリア・エリザベト
小説家、日本芸術院会員、女流文学者会会員、日本文芸家協会理事、日本財団会長、海外邦人宣教者活動援助後援会代表、脳死臨調委員、世界の中の日本を考える会理事、松下政経塾理事、国際長寿社会リーダーシップセンター理事、日本オーケストラ連盟理事。
昭和6年9月17日生、東京都出身。29年3月聖心女子大学英文科卒。
28年、小説家で元文化庁長官の三浦朱門氏と結婚。29年、「遠来の客たち」で芥川賞候補となり文壇デビュー。作家として執筆、講演活動をこなす一方、日本財団会長や日本文芸家協会理事、その他政府諮問機関委員など多数の公職を務める他、敬虔なカトリック系クリスチャンでもあり、民間援助組織(ngo)である海外邦人宣教者活動援助講演会代表も務める。特に、この後援会での25年間にわたる活動が高く評価され、第4回読売国際協力賞を受賞した。
45年、エッセイ「誰のために愛するか」が200万部のベストセラーに。54年「神の汚れた手」で、第19回女流文学賞にノミネートされたが辞退。59年臨教審委員。平成5年日本芸術院会員。日本財団理事を経て、7年会長に就任。最近、発表した作品は、海外邦人宣教者活動援助後援会の記録を著した「神様、それをお望みですか」がある。
その他の主な作品:「無名碑」「地を潤すもの」「紅梅白梅」「奇蹟」「神の汚れた手」「時の止まった赤ん坊」「砂漠、この神の土地」「湖水誕生」「夜明けの新聞の匂い」「天井の青」「二十一世紀への手紙」「極北の光」など。
【受賞歴】
1979年 ローマ法王庁よりヴァチカン有功十字勲章
1987年 「湖水誕生」により土木学会著作賞を受賞
1988年 フジ・サンケイグループより鹿内信隆正論大賞受賞
1992年 韓国・宇耕(ウギョン)財団より文化芸術賞
1993年 第49回日本芸術院賞恩賜賞
1995年 第46回日本放送協会放送文化賞
1997年 読売国際協力賞
1998年 財界賞特別賞
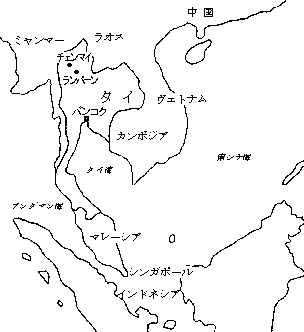
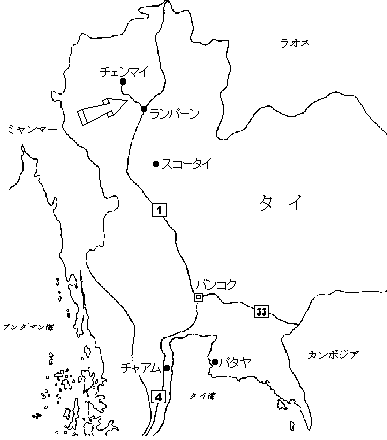
 ――現場にはそうした人知れぬ苦労や美談も多いのに、土木は3kなどと言われてきました。そうしたイメージを回復するには、何が必要と考えますか
――現場にはそうした人知れぬ苦労や美談も多いのに、土木は3kなどと言われてきました。そうしたイメージを回復するには、何が必要と考えますか